プロが厳選!2024年夏に学ぶべき技術トレンド5選【実践コード付き】
アフィリエイト開示

はじめに
こんにちは!長年、システム開発の現場で働きながらプログラミング教育にも携わっている技術者です。めまぐるしく変化するIT業界では、「次に何を学ぶべきか?」と悩むことが多いですよね。特に新しい技術が次々と登場する今、その情報の波に乗り遅れないようにするのは大変です。
この記事では、2024年の夏にぜひ押さえておきたい技術トレンドを、私の経験から5つ厳選してご紹介します。単なる技術の羅列ではなく、「なぜ今この技術が重要なのか」「どんなプロジェクトで役立つのか」といった実践的な視点を大切にしました。初心者の方が最初の一歩を踏み出すための技術から、チーム開発や将来のキャリアを見据えた技術まで、幅広くカバーしています。
この記事を読むことで、あなたの次の学習目標が明確になり、スキルアップへの具体的な道筋が見えてくるはずです。さあ、一緒に未来を創る技術の世界を探検しましょう!
【技術・ツール1】初心者におすすめ:Svelte 5
特徴と魅力
Svelteは、ReactやVue.jsと同じくユーザーインターフェースを構築するためのフレームワークですが、根本的なアプローチが異なります。Reactなどが実行時に仮想DOMを使って差分を更新するのに対し、Svelteはコンパイラとして動作します。つまり、開発者が書いたコードを、ビルド時に素のJavaScriptの命令に変換してしまうのです。これにより、バンドルサイズが小さくなり、実行時パフォーマンスが非常に高いという特徴があります。
そして2024年、待望の「Svelte 5」がリリースされ、その中心的な機能である「Runes(ルーン)」が大きな注目を集めています。これは、コンポーネントの状態管理をより直感的かつパワフルにするための新しい仕組みです。これまで以上にコードがシンプルになり、React Hooksのような複雑なルールを覚える必要もありません。この学習コストの低さとパフォーマンスの高さが、特に初心者の方におすすめしたい理由です。
実際の使用例とコード
Svelte 5のRunesを使った、シンプルなカウンターアプリを作ってみましょう。驚くほどコードが少ないことに気づくはずです。
<!-- Counter.svelte -->
<script>
// $stateでリアクティブな状態を宣言します
let count = $state(0);
function increment() {
count += 1;
}
// $derivedは他の状態から計算される値を宣言します
let double = $derived(count * 2);
// $effectは状態が変化したときに副作用(例: console.log)を実行します
$effect(() => {
console.log(`現在のカウントは ${count} です。`);
});
</script>
<h1>Svelte 5 Counter</h1>
<p>Count: {count}</p>
<p>Double: {double}</p>
<button on:click={increment}>
Click me
</button>
<style>
button {
font-size: 1.2em;
padding: 0.5em 1em;
border-radius: 8px;
}
</style>コード解説:
let count = $state(0);:$stateを使ってcountという変数を宣言するだけで、この変数が変更されると自動的にUIが更新されるようになります。これがリアクティブな状態です。let double = $derived(count * 2);:$derivedは、countの値に依存する派生的な状態を作ります。countが変わればdoubleも自動的に再計算されます。<button on:click={increment}>:ボタンがクリックされたときにincrement関数を呼び出します。この関数内でcountを更新すると、{count}と{double}が表示されている部分が即座に新しい値に変わります。
学習のコツと注意点
Svelteを学ぶ一番の近道は、公式ウェブサイトにあるインタラクティブなチュートリアルを試すことです。実際にブラウザ上でコードを書きながら基本を学べるので、非常に効率的です。最初は小さなコンポーネントをたくさん作ってみましょう。失敗を恐れずに、「こう書いたらどうなるんだろう?」と実験を繰り返すことが上達の秘訣です。
注意点として、SvelteはまだReactやVueに比べてエコシステム(ライブラリやツール群)が小さい面があります。しかし、主要な機能は揃っており、コミュニティも活発なので、今後さらに充実していくでしょう。
どんな人・プロジェクトに向いているか
- Webフロントエンド開発の初心者:覚えることが少なく、直感的に開発を始められます。
- 個人開発者やスタートアップ:高速なプロトタイピングと高いパフォーマンスが求められるプロジェクトに最適です。
- パフォーマンスを重視するWebサイト:ブログやランディングページなど、表示速度が重要なサイトに向いています。
【技術・ツール2】効率性重視:GitHub Copilot Workspace

特徴と魅力
GitHub Copilotは、AIがコード補完をしてくれるツールとして既に多くの開発者に利用されていますが、「Copilot Workspace」はその進化形です。これは単なるコード補完ツールではありません。「アイデアから実装までのプロセス全体をAIが支援する」という、まったく新しい開発体験を提供します。
具体的には、GitHubのIssue(課題や機能要望)に「〇〇という機能を作りたい」と自然言語で書くだけで、Copilot Workspaceがその実現に必要な仕様を整理し、変更すべきファイルのリストアップ、そして具体的なコードの変更案までを自動で生成してくれます。開発者は、AIが提案した計画とコードを確認・修正し、承認するだけでプルリクエストを作成できます。これにより、開発の初期段階にかかる時間と労力を劇的に削減できるのです。
実際の使用例とコード
Copilot WorkspaceはGUIベースのツールのため、直接的なコード例はありません。代わりに、典型的な利用シナリオを紹介します。
- Issueの作成:GitHubリポジトリに「ユーザープロフィールページに自己紹介欄を追加する」というIssueを作成します。
- Workspaceの起動:IssueからCopilot Workspaceを起動します。
- 仕様の確認:AIが「データベースのUserモデルに
bioカラムを追加」「プロフィール表示用のAPIを修正」「フロントエンドのUIコンポーネントにテキストエリアを追加」といった具体的な計画(Spec)を提案してくれます。 - 実装案の生成:開発者が計画を承認すると、AIが実際のコード変更案(Implementation)を生成します。これには、データベースのマイグレーションファイル、バックエンドのAPIコード、フロントエンドのHTML/CSS/JavaScriptの変更が含まれます。
- レビューと修正:開発者はAIが生成したコードをレビューし、必要に応じて手動で修正を加えます。
- プルリクエストの作成:内容に問題がなければ、ボタン一つでプルリクエストを作成し、チームメンバーにレビューを依頼できます。
この流れにより、面倒な定型作業やファイルを探す手間から解放され、より創造的な部分に集中できます。
学習のコツと注意点
Copilot Workspaceを使いこなすコツは、「AIへの的確な指示出し」です。Issueに書く要望は、具体的で明確なほどAIの提案の精度が上がります。最初は小さなタスクから試してみて、AIとの対話に慣れるのが良いでしょう。
注意点として、AIが生成するコードは完璧ではありません。必ず人間の目でレビューし、プロジェクトのコーディング規約や設計思想に合っているかを確認するプロセスが不可欠です。AIは強力な副操縦士(Copilot)であり、最終的な判断を下すのはあくまでパイロットであるあなた自身です。
どんな人・プロジェクトに向いているか
- すべてのソフトウェア開発者:新規機能開発やリファクタリングの効率を飛躍的に向上させたい人。
- アジャイル開発チーム:短期間でプロトタイプを作成し、素早くイテレーションを回したいチーム。
- オープンソースプロジェクト:コントリビューターが開発を始める際のハードルを下げることができます。
【技術・ツール3】チーム開発向け:OpenTelemetry
特徴と魅力
現代のシステムは、複数の小さなサービスが連携して動作する「マイクロサービスアーキテクチャ」が主流です。しかし、サービスが分散すると、問題が発生したときに「どこで何が起きているのか」を特定するのが非常に難しくなります。この課題を解決するのが「可観測性(Observability)」という考え方であり、それを実現するための標準規格がOpenTelemetryです。
OpenTelemetryは、アプリケーションの動作状況を把握するための3つの主要なデータ(トレース、メトリクス、ログ)を、統一された仕様で収集・送信するためのツールキットを提供します。最大の魅力は、特定の監視ツール(Datadog, New Relicなど)に依存しないベンダーニュートラルな点です。一度OpenTelemetryを導入すれば、将来的に監視ツールを乗り換える際も、アプリケーション側のコードをほとんど変更する必要がありません。これは、長期的なシステムの保守性において非常に大きなメリットです。
実際の使用例とコード
Node.jsとExpressを使った簡単なWebサーバーに、OpenTelemetryを導入してリクエストのトレース情報をコンソールに出力する例を見てみましょう。
// tracer.js
// OpenTelemetryの基本的な設定ファイル
const { NodeSDK } = require('@opentelemetry/sdk-node');
const { ConsoleSpanExporter } = require('@opentelemetry/sdk-trace-node');
const { getNodeAutoInstrumentations } = require('@opentelemetry/auto-instrumentations-node');
const sdk = new NodeSDK({
// トレース情報をコンソールに出力するエクスポーターを設定
traceExporter: new ConsoleSpanExporter(),
// Expressなどの主要なライブラリを自動で計装する設定
instrumentations: [getNodeAutoInstrumentations()]
});
sdk.start();
console.log('OpenTelemetry tracing initialized');
// アプリケーション終了時にSDKもシャットダウンする
process.on('SIGTERM', () => {
sdk.shutdown()
.then(() => console.log('Tracing terminated'))
.catch((error) => console.log('Error terminating tracing', error))
.finally(() => process.exit(0));
});// app.js
// Expressを使ったWebサーバー本体
// tracer.jsを最初に読み込むことが重要
require('./tracer');
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;
app.get('/', (req, res) => {
res.send('Hello, OpenTelemetry!');
});
app.listen(port, () => {
console.log(`Example app listening on port ${port}`);
});実行方法:
npm install express @opentelemetry/sdk-node @opentelemetry/sdk-trace-node @opentelemetry/auto-instrumentations-nodeを実行します。- 上記の2つのファイルを保存し、
node app.jsでサーバーを起動します。 - ブラウザやcurlで
http://localhost:3000/にアクセスすると、ターミナルにリクエストに関する詳細なトレース情報が出力されます。
学習のコツと注意点
OpenTelemetryの学習は、まず「トレース」の概念を理解することから始めましょう。リクエストがシステム内のどのサービスを、どの順番で、どれくらいの時間をかけて通過したのかを可視化する技術です。自分の手元で動く小さなアプリケーションに導入し、実際にトレース情報が出力されるのを確認するのが一番の近道です。
注意点として、設定が少し複雑に感じられるかもしれません。しかし、公式ドキュメントには各言語ごとの丁寧なガイドが用意されています。焦らず一つずつ設定の意味を理解していくことが大切です。
どんな人・プロジェクトに向いているか
- バックエンドエンジニア、SRE(Site Reliability Engineer):システムの安定稼働とパフォーマンス監視に責任を持つ人。
- マイクロサービスアーキテクチャを採用しているプロジェクト:サービス間の連携を可視化し、障害調査を効率化したい場合。
- 将来的な技術的負債を避けたいチーム:ベンダーロックインを防ぎ、保守性の高いシステムを構築したいチーム。
【技術・ツール4】将来性重視:WebAssembly (WASM)
特徴と魅力
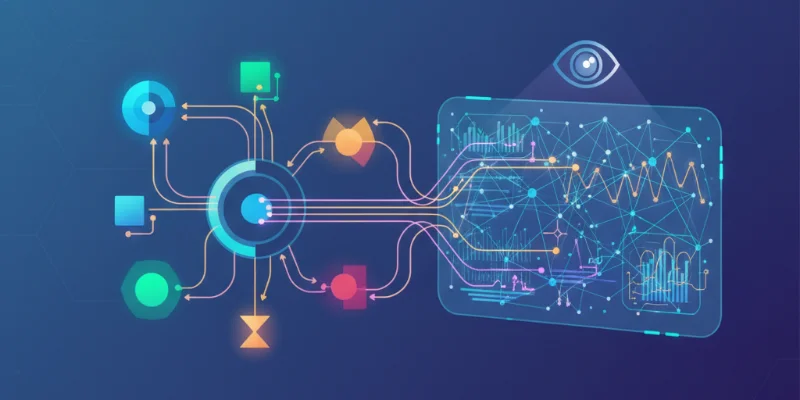
WebAssembly(通称WASM)は、Webブラウザで実行できる新しい種類のコードです。JavaScriptとは異なり、バイナリ形式の命令セットであるため、非常に高速に動作します。元々はC++やRustといった高性能な言語で書かれたコードをWeb上で動かすために開発されましたが、その可能性はブラウザの外にも広がっています。
WASMの主な魅力は次の3つです。
- 高速性:ネイティブコードに近いパフォーマンスを発揮します。動画編集、ゲーム、画像処理など、高い計算能力が求められる分野で威力を発揮します。
- 安全性:WASMはサンドボックス環境で実行されるため、ホストシステム(ブラウザやサーバー)の他の部分に影響を与えることができません。これにより、安全なプラグインシステムなどを構築できます。
- 言語非依存:C++, Rust, Go, C#など、多くの言語からWASMへコンパイルできます。開発者は得意な言語を使って高性能なモジュールを開発できます。
最近では、WASI(WebAssembly System Interface)という標準も策定され、サーバーサイドやエッジコンピューティング環境でもWASMが使われるようになり、将来性が非常に期待されています。
実際の使用例とコード
ここでは、Rustで書いた簡単な足し算関数をWASMにコンパイルし、JavaScriptから呼び出す例を紹介します。wasm-packというツールを使うと非常に簡単です。
-
Rustプロジェクトのセットアップ
cargo new --lib wasm-exampleでライブラリプロジェクトを作成します。 -
Rustコードの記述
// src/lib.rs
use wasm_bindgen::prelude::*;
// このアノテーションで、この関数がJavaScriptから呼び出せるようになる
#[wasm_bindgen]
pub fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {
a + b
}-
WASMへのコンパイル プロジェクトのルートで
wasm-pack build --target webを実行します。するとpkgディレクトリが生成され、必要なファイルがすべて揃います。 -
JavaScriptからの呼び出し
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>WASM Example</title>
</head>
<body>
<script type="module">
// wasm-packが生成したモジュールをインポート
import init, { add } from './pkg/wasm_example.js';
async function run() {
// WASMモジュールを初期化
await init();
const result = add(5, 7);
console.log('WASMからの計算結果:', result); // 12が出力される
alert(`5 + 7 = ${result}`);
}
run();
</script>
</body>
</html>このHTMLファイルをWebサーバーで開くと、Rustで書かれたadd関数が実行され、結果がアラートで表示されます。
学習のコツと注意点
WASMを始めるには、RustやC++など、コンパイル対象となる言語の基礎知識が必要です。特にRustは、メモリ安全性が高くWASMとの相性が良いためおすすめです。まずは、今回のような簡単な関数をJavaScriptから呼び出す「小さな成功体験」を積むことから始めましょう。JavaScriptとWASMの間で複雑なデータをやり取りする方法など、少しずつステップアップしていくのが良いでしょう。
どんな人・プロジェクトに向いているか
- Webゲーム開発者:高いパフォーマンスが求められるゲームロジックの実装に。
- 計算量の多いWebアプリケーション開発者:画像・動画処理、科学技術計算、CADツールなど。
- クロスプラットフォームなライブラリを開発したい人:一度WASMで書けば、Web、サーバー、モバイルなど様々な環境で再利用できます。
【技術・ツール5】応用力重視:Local LLM (Ollama)
特徴と魅力
ChatGPTなどのクラウドベースのAIサービスは非常に強力ですが、プライバシーの懸念やAPIの利用料金、オフラインで使えないといった制約があります。こうした課題を解決するのが、自分のPC上で大規模言語モデル(LLM)を実行する「Local LLM」というアプローチです。
その中でも「Ollama」は、様々なオープンソースLLMを非常に簡単にセットアップし、実行できるツールとして注目を集めています。数行のコマンドを実行するだけで、Llama 3やMistralといった高性能なモデルを自分のマシンで動かすことができます。
Local LLMの魅力は以下の通りです。
- プライバシー:データが外部のサーバーに送信されないため、機密情報や個人情報を扱うアプリケーションにも安心して利用できます。
- コスト:一度モデルをダウンロードすれば、API利用料を気にせず何度でも使えます。
- カスタマイズ性:特定のタスクに特化したモデルをファインチューニング(追加学習)することも可能です。
- オフライン利用:インターネット接続がない環境でもAI機能を利用できます。
実際の使用例とコード
Ollamaを使って、Pythonから簡単なチャットボットを実装してみましょう。
-
Ollamaのインストールとモデルのダウンロード Ollamaの公式サイトからインストーラをダウンロードして実行します。その後、ターミナルで以下のコマンドを実行してモデルをダウンロードします。
ollama pull llama3 -
PythonからのAPI利用 OllamaはローカルにAPIサーバーを立ててくれるので、
requestsライブラリを使って簡単にアクセスできます。
# chat.py
import requests
import json
# Ollama APIのエンドポイント
url = "http://localhost:11434/api/chat"
# チャットの履歴を保持するリスト
messages = []
print("チャットボットを開始します。終了するには 'exit' と入力してください。")
while True:
user_input = input("あなた: ")
if user_input.lower() == 'exit':
break
# ユーザーの入力を履歴に追加
messages.append({"role": "user", "content": user_input})
# Ollamaに送信するデータ
data = {
"model": "llama3",
"messages": messages,
"stream": False # ストリーミングを無効にして一度にレスポンスを受け取る
}
# APIにリクエストを送信
response = requests.post(url, json=data)
# レスポンスからAIの返答を取得
response_data = response.json()
bot_message = response_data['message']['content']
print(f"ボット: {bot_message}")
# AIの返答も履歴に追加
messages.append({"role": "assistant", "content": bot_message})実行方法:
pip install requests を実行した後、python chat.py でスクリプトを実行すると、ターミナル上でAIとの対話が始まります。
学習のコツと注意点
まずはOllamaをインストールし、コマンドラインでollama run llama3のようにして直接モデルと対話してみるのが最初のステップです。次に、今回のようにPythonやJavaScriptからAPIを叩いて、自分のアプリケーションにAI機能を組み込んでみましょう。どのようなプロンプト(指示)を与えると良い結果が得られるか、試行錯誤すること自体が学びになります。
注意点として、高性能なモデルは多くのメモリ(RAM)やVRAM(GPUメモリ)を必要とします。自分のPCのスペックを確認し、適切なサイズのモデルを選ぶことが重要です。
どんな人・プロジェクトに向いているか
- AIアプリケーション開発者:プライバシーを重視したAIチャットや、ドキュメント要約ツールなどを開発したい人。
- データサイエンティスト・研究者:手元のデータを使ってモデルの実験やファインチューニングを行いたい人。
- 新しい技術を試したいホビイスト:自分のPCだけで最先端のAI技術を動かしてみたい人。
選択と学習の戦略
ここまで5つの魅力的な技術を紹介してきましたが、「どれから学べばいいの?」と迷ってしまうかもしれません。ここでは、あなたの状況に合わせた学習戦略を提案します。
複数技術の学習順序
- Web開発者を目指すなら:まずは「Svelte 5」でフロントエンドの基礎と楽しさを学びましょう。次に、バックエンドに興味があれば「OpenTelemetry」でシステムの裏側を覗いてみると、より広い視野が身につきます。
- 生産性を劇的に上げたいなら:「GitHub Copilot Workspace」を日々の開発に導入してみましょう。これは特定の言語を学ぶというより、開発スタイルそのものを変えるためのツールです。
- AIや最先端技術に挑戦したいなら:「Local LLM (Ollama)」から始めるのが手軽でおすすめです。その後、よりパフォーマンスが求められる分野に興味が湧いたら「WebAssembly」に挑戦すると、作れるものの幅が大きく広がります。
大切なのは、すべてを一度にやろうとしないことです。一つ選んで集中し、ある程度自信がついたら次の技術に進む、というステップを踏みましょう。
効率的な習得方法
- 公式ドキュメントこそ最高の教科書:新しい技術を学ぶときは、まず公式のチュートリアルやドキュメントに目を通しましょう。最も正確で最新の情報がそこにあります。
- 手を動かして小さなものを作る:知識をインプットするだけでなく、必ずアウトプットしましょう。「学んだ技術を使って、自分のための小さなツールを作る」のが最も効果的です。例えば、SvelteでTodoアプリ、Ollamaで日記の自動要約ツールなど。
- エラーを恐れない:プログラミング学習にエラーはつきものです。エラーメッセージをしっかり読み、解決策を探すプロセスこそが、あなたを成長させてくれます。試行錯誤を楽しんでください。
実践での活用アプローチ
- 既存プロジェクトに小さく導入:いきなり大規模なプロジェクトに導入するのはリスクが高いです。まずは個人プロジェクトや、業務であれば影響の少ない社内ツールなどで試してみましょう。
- 学んだことを発信する:ブログ記事を書いたり、勉強会で発表したりすることで、自分の理解が深まるだけでなく、同じ技術に興味を持つ仲間と繋がることができます。
- チームで試す:もしチームで開発しているなら、「この新しいツールを少し試してみませんか?」と提案してみましょう。チームで知識を共有しながら学ぶことで、より早く、より深く技術を習得できます。
まとめ:成長につながる技術選択
今回は、2024年夏に注目すべき5つの技術トレンドをご紹介しました。Svelte 5のシンプルさ、Copilot Workspaceの効率性、OpenTelemetryの堅牢性、WebAssemblyの将来性、そしてLocal LLMの応用力。それぞれに異なる魅力があり、あなたのエンジニアとしての可能性を広げてくれるはずです。
覚えておいてほしいのは、技術はあくまで「何かを実現するための手段」であるということです。流行っているからという理由だけで学ぶのではなく、「この技術を使えば、あの問題を解決できるかもしれない」「こんな面白いものが作れるかもしれない」というワクワクする気持ちを大切にしてください。
学びの旅に終わりはありません。今日紹介した技術の中から一つでも興味を持ったものがあれば、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。応援しています!
関連商品・おすすめアイテム

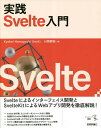
![[書籍] 実践 SVELTE入門【10,000円以上送料無料】(ジッセンスベルトニュウモン)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/gakuhu/cabinet/m97842971/m9784297134952.jpg?_ex=128x128)



